阿部一二三選手が「筋トレをしない」と語った真意とは?
柔道界きっての実力者である彼が放ったこの発言は、多くの柔道ファンやトレーニーの間で議論を呼んでいます。
しかしその言葉の裏には、単なるトレーニング否定ではない、柔道という競技特性への深い理解と、自身の戦い方への確固たる信念が隠されているのです。
- 阿部選手が「筋トレをしない」と語った文脈と背景
- 柔道におけるトレーニング論争の最前線
- 技術偏重なのか、それとも隠れたフィジカルメニューが?
- 他選手との比較で見える“柔道家の多様性”
- これからの柔道界に求められるトレーニングの在り方
この記事では、阿部一二三選手が筋トレを「しない」と発言する背景を深掘りしながら、柔道界全体のトレーニング観にも迫ります。筋トレ至上主義では語れない、“技と感覚”の世界をご紹介します。
阿部一二三が筋トレをしないと言われる理由
柔道界を代表するトップアスリート、阿部一二三選手。「筋トレをしない」という彼の発言は、多くの人に驚きを与えました。筋トレ=強さという図式が一般的に浸透している中で、なぜ彼はそのような考えを示したのでしょうか?このセクションでは、筋トレを行わないという発言の背景にある戦略や哲学を紐解き、柔道家としての阿部選手のスタイルを深掘りしていきます。
現役選手にも関わらず「筋トレしない」発言
阿部一二三選手はテレビ番組やインタビューなどでたびたび「自分は筋トレをしていない」と発言しています。この言葉が単独で切り取られた結果、彼がトレーニングそのものを否定しているかのように誤解された面もあります。しかし、実際には「一般的なウエイトトレーニングやマシントレーニングに頼らない」という意味合いが強く、柔道に最適化されたトレーニングに集中しているのです。
実戦を重視する柔道スタイル
阿部選手の練習は、筋肉を鍛えるよりも「実際の柔道の動き」を中心に据えています。打ち込み・投げ込み・乱取り(スパーリング)といった実践型トレーニングが主で、身体操作や技のタイミングを高めることに重点を置いています。
- 筋トレ=筋力の強化に偏重しない
- 実戦の中で鍛える“使える筋肉”を重視
- 筋トレよりも「柔道そのもの」に集中することを優先
筋肉ではなく“感覚”と“間”の強さ
阿部一二三選手が重視するのは「間合い」や「タイミング」といった感覚的な要素です。筋力で押し切るスタイルではなく、相手の動きを読む直感、そして一瞬の反応力が重要視されています。これは幼少期からの積み重ねで培われてきた“感覚”の領域であり、単なるフィジカルでは得られない部分です。
技術練習とスパーリングが中心
彼の一日のトレーニング内容を見ると、朝から晩まで技術系の稽古がびっしり組み込まれています。
| 時間帯 | トレーニング内容 |
|---|---|
| 午前 | 打ち込み・投げ込み |
| 午後 | 乱取り(実戦稽古) |
| 夜 | ストレッチ・回復系トレーニング |
このように、技術を高める実戦的な稽古に多くの時間を割いており、これこそが彼の強さの源泉なのです。
SNSでの発言が独り歩きしている
「筋トレしない」発言が一人歩きした要因の一つがSNSです。発言の文脈を無視して「阿部一二三=筋トレ嫌い」というイメージが広まったことにより、実態とは異なる認識が形成されました。
- 本人の意図とは異なる切り取り方
- フォロワー同士の解釈が加熱
- 見出しやサムネイルの影響
その結果、「筋トレをしない柔道家」というイメージが出来上がってしまったのです。
柔道選手にとって筋トレは本当に必要か
筋トレを取り入れるか否か――これは柔道界において常に議論の的となってきました。フィジカルを重視する選手もいれば、技術や感覚に偏重する選手もいます。阿部一二三選手のようなスタイルは、後者に分類されますが、これが成功を収めている事実も無視できません。このセクションでは、柔道における筋トレの必要性を多角的に検証します。
筋トレ肯定派と否定派の違い
筋トレ肯定派は、「筋力があれば投げも返しも効く」という考えに基づいており、試合中に押し負けないフィジカルが勝利を左右すると考えています。対して、否定派は「力より技」「力任せの柔道は通用しない」とする技術偏重型です。
この2つのスタイルの対比は、トレーニング内容の違いにも表れています。
| スタイル | トレーニング特徴 |
|---|---|
| 肯定派 | ベンチプレス・スクワット・デッドリフトなどを導入 |
| 否定派 | 投げ込み・乱取り・足さばき・受け身練習など |
試合に勝つために必要な要素とは
試合で勝つために本当に重要なのは、「技術」「戦略」「体力」「精神力」の4つです。筋力はこの中の一部に過ぎず、それだけでは勝ち切れないのが柔道という競技です。
阿部一二三選手は、戦略と技術の融合、さらに研ぎ澄まされた感覚で相手を崩すスタイルを確立しており、それが筋トレよりも実戦を重視する理由の一つでもあります。
フィジカルよりも戦術理解が重要
柔道は「相手との駆け引き」が命です。力任せに攻め込むよりも、相手の重心の乱れを読んで、タイミングよく仕掛ける方が有効です。戦術の理解が浅いと、どんなに筋肉があっても試合運びでミスを犯してしまいます。
- 投げのタイミング=感覚の勝負
- 相手のくせ・重心移動を読む分析力
- 筋力は補助的な役割にとどまる
以上が、阿部一二三選手が「筋トレしない」理由を合理的に裏付ける要素であり、柔道の特性に合わせた独自のスタイルなのです。
阿部一二三が取り入れるフィジカルトレーニングの実態
「筋トレをしない」と語る阿部一二三選手ですが、全く体を鍛えていないわけではありません。彼が重視しているのは、柔道に必要な“実用的な身体能力”を養うトレーニングです。つまり、単にバーベルを上げるのではなく、体幹・柔軟性・バランスなど、競技に直結する能力を日々磨いているのです。このセクションでは、彼の“筋トレとは異なるフィジカルトレーニング”の実態に迫ります。
筋トレに代わる体幹・バランストレーニング
阿部選手は、一般的な筋力強化ではなく、柔道の動きに必要な体幹力とバランス感覚を鍛えるトレーニングを行っています。代表的なものに以下があります。
- バランスボールを活用した不安定トレーニング
- プランクやツイストを含む静的体幹トレ
- 片足スクワットによる左右バランス強化
これらは、対戦中に崩されそうな体勢を維持したり、投げを仕掛ける際の軸を安定させるために欠かせないトレーニングです。
柔軟性を重視した身体操作の向上
阿部一二三選手の身体操作は、非常に柔らかく、関節の可動域も広いのが特徴です。これは日常的に行っているストレッチや可動域拡大のトレーニングによる成果です。特に重要視しているのは、
| 部位 | 目的 |
|---|---|
| 股関節 | 足技や巴投げの安定感向上 |
| 肩甲骨 | 引き手の動きを滑らかに |
| 腰まわり | 腰投げの回転力と反応速度向上 |
柔軟性を保つことで、怪我の予防とともに、スムーズな動きが実現します。
怪我予防としての補強運動
阿部選手は、怪我の多い競技である柔道において、怪我を未然に防ぐ“補強運動”にも力を入れています。これは筋肉を大きくする目的ではなく、関節や腱を支える筋肉群を整えるための運動です。
主な補強メニュー:
- ゴムチューブを使ったインナーマッスル強化
- 関節可動域に合わせた関節補強
- 弱点部位の筋持久力アップ
“筋肉を増やす”のではなく、“身体を守る”ためのトレーニング――これが阿部選手のフィジカル戦略なのです。
なぜ誤解されるのか?報道やSNSの影響
「筋トレをしない=トレーニング全般を否定している」といった誤解が広まった背景には、報道やSNSの影響があります。このセクションでは、どうしてそのような認識が生まれてしまったのか、そのプロセスを具体的に追っていきます。
「筋トレしない」発言の文脈を無視
阿部選手が出演した番組やインタビューでは、「筋トレはしていないが、実戦で鍛えることが大切」という趣旨の発言がありました。ところが、タイトルやハイライトでは「筋トレしてない」という部分だけがピックアップされ、文脈のニュアンスが省かれてしまったのです。
例:
「阿部一二三、筋トレは全くしない!」
といったタイトルでは、本質が伝わりません。
メディアの切り取りとタイトル誤認
YouTubeやニュースメディアでは「インパクト重視の編集」が行われることが多く、視聴数やクリック数を稼ぐためにセンセーショナルな表現が使われます。その結果、阿部選手の本来の意図とは異なる形で拡散されてしまうことがあるのです。
視聴者や読者は「タイトル」や「最初の一言」だけで内容を判断しがちで、深く内容を読み取ることなく誤認するケースもあります。
ファンの間で拡散されたミスリード
SNSでは、発言の一部を切り取って拡散する“切り抜き文化”が存在します。「阿部一二三=筋トレ嫌い」「筋肉を否定する柔道家」などのイメージが先行し、いつの間にかそれが“事実”のように広まってしまうのです。
さらに、SNSの特性上、拡散スピードが速く、一度拡散された誤情報は訂正が難しくなるため、本人の真意が正しく届かないという現象も起きています。
情報の受け取り手の責任も重要です。誰かの言葉を引用する際には、前後の文脈を含めて理解することが、真実に近づく第一歩です。
このように、報道とSNSが交錯することで、阿部選手の意図しないイメージが形成されたと言えるでしょう。
他のトップ柔道家との筋トレ比較
阿部一二三選手が「筋トレをしない」と語る一方で、他のトップ柔道家たちはどうでしょうか?このセクションでは、国内外の有力選手と比較することで、トレーニングの多様性と個人差について明らかにしていきます。
ウルフアロン選手のウエイト重視型
東京五輪金メダリストのウルフアロン選手は、フィジカルを強化するために、徹底したウエイトトレーニングを行うスタイルです。実際にSNSなどでは、ベンチプレスやスクワットのトレーニング風景を頻繁に投稿しており、その筋肉量は格闘家顔負けです。
- 筋力と体格の優位性を活かした組み手戦術
- トレーニングと栄養管理を徹底
- 1回の試合に向けたピーキング管理も
彼のように、「筋肉を武器にする柔道家」も一定数存在します。
永瀬貴規選手の持久力優先型
永瀬選手はウエイトよりも持久系や有酸素運動を重視しています。1日に20km近く走ることもあるとされ、乱取りの後でも動きが鈍らないタフさが特徴です。
持久力トレーニングの一例:
| 種目 | 目的 |
|---|---|
| 長距離ラン | 基礎体力と心肺機能の強化 |
| サーキットトレーニング | 試合中の疲労耐性アップ |
| HIIT | 短時間高負荷での心肺適応 |
このように、永瀬選手は“スタミナで勝つ”タイプの柔道家です。
海外選手とのトレーニング観の違い
ヨーロッパやロシア、ブラジルといった柔道強豪国では、一般的に筋トレの比重が非常に高く、筋肉美と競技力を直結させる文化があります。たとえば、ロシアの選手たちは日々高重量を扱うトレーニングを継続しており、ウェイトを基盤に柔道を組み立てる傾向があります。
一方、日本では、古来からの“技を磨く”という流派的文化も強く、フィジカルと技術のバランスに重きを置く傾向があります。阿部選手はまさにその“技術重視”の系譜に位置しており、それが彼の強さの根源にもなっています。
今後の柔道界におけるトレーニングの在り方
「筋トレをしない」という選択肢が表すのは、単なる個人の好みではありません。それは、これからの柔道界が向かうべきトレーニングの在り方そのものを問うメッセージとも捉えられます。ここでは、柔道の未来に向けたトレーニングバランスの在り方を考察します。
次世代に必要とされるトレーニングバランス
過去の柔道では「根性・反復」が重視されていましたが、近年ではスポーツ科学に基づいた戦略的トレーニングが重視されています。筋力・持久力・柔軟性・反応速度・判断力……全てがバランス良く整ってこそ、真のトップアスリートとなるのです。
未来の柔道には、以下のようなトレーニングモデルが求められるでしょう:
- 筋力+感覚のハイブリッド育成
- 試合分析から逆算した戦術的トレーニング
- データを活用した個別メニューの最適化
個人特性に合わせた柔軟なアプローチ
選手ごとに体格・骨格・柔軟性・気質が異なるため、画一的な筋トレを押し付ける時代は終わりを迎えています。阿部一二三選手のように「技で勝つタイプ」もいれば、ウルフアロン選手のように「パワーで押し切るタイプ」もいます。
重要なのは、「自分に合った方法を選び、信じて継続すること」です。
“筋トレ=正義”ではない未来
近年、フィジカル至上主義のスポーツ観は揺らぎつつあります。特に日本武道においては、技術・精神・身体の三位一体が理想とされています。
筋トレはあくまで一つの手段であり、目的ではない。「筋トレが全て」ではなく、「自分のスタイルを活かす手段の一つ」という捉え方が、次世代の柔道にとってより現実的で実りあるアプローチとなるでしょう。
阿部一二三選手のようなスタイルが脚光を浴びることで、「トレーニングに正解は一つではない」という柔道界の価値観が再認識されつつあります。
筋トレという選択をあえて外す――そこにこそ、今後の柔道の進化を支える重要な視座があるのです。
まとめ
「筋トレをしない」という言葉が、一人歩きして誤解を生んでいる――そんな現象が、阿部一二三選手を取り巻く報道やSNS上で起きています。
しかし実際には、彼がまったくトレーニングをしていないわけではありません</span。柔道という競技における技術と間合い、そして爆発的な一瞬の力を重視するスタイルが、阿部選手の信念に繋がっているのです。
フィジカルを極める者もいれば、感覚と技術に磨きをかける者もいる――
柔道は「多様な強さ」が共存する競技であり、その中で阿部一二三というスタイルは唯一無二の存在感を放っています。
今後は、“筋トレをしない”といった発言が持つ意味を一面的に捉えるのではなく、選手の戦術・哲学・トレーニング理論を包括的に理解する視点が求められるでしょう。

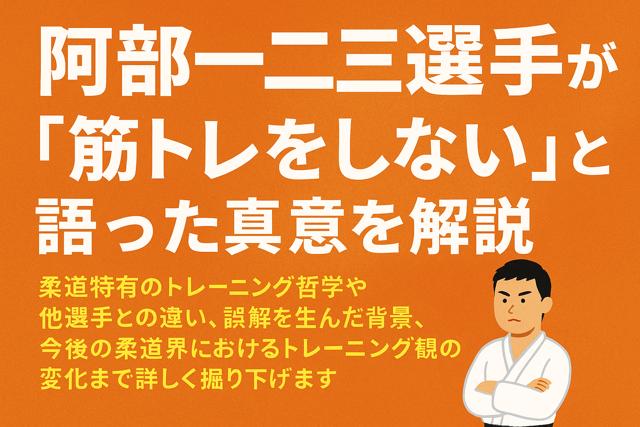


コメント